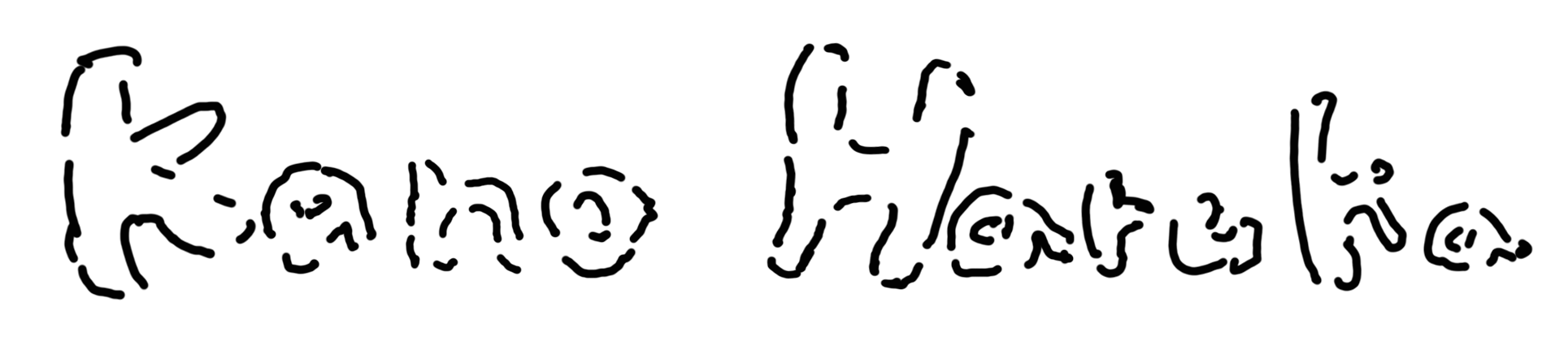私は、絵から画面の外まで、ひいては見ている人の背後にまでまわりこむことができるような空間の広がりを持った絵、「サラウンド感」のある絵をつくりたいと思っている。それは、風景「である」絵を目指しているからだ。
ふつう風景画は、実際に外にある風景を画面に描き写すなどの方法でつくられる。その絵を見る人はおそらく、絵から実際の風景を想起する。それは往々にして「絵として風景を見ている」のであって、その絵はあくまで風景を描いた絵だ。
私はそうではなく「風景として絵を見る」ことができる絵、見る時に、当然絵ではあるが風景でもあるような、そんなリアリティをともなった体感のある絵をつくりたい。
そもそも、絵は限られた画面だが、実際の風景には周囲に空間が広がっている。実際に外で風景を見ているときには、背後までもあるこの空間広がりの感覚こそが大事なのではないか。(私はこの広がりの感覚を「サラウンド感」と呼んでいる。)
ならば、画面以上に広がる感覚を呼び起こすような絵をつくれば、風景であるような絵になるのではないか。
この考えから絵が、線や絵の具のしみのような色斑といった絵の中の要素から風景的なシステムによって組み上がり、その空間が「風景」として立ち現れるという現在の制作過程ができた。
その中で重要なのは、見る人の視線により空間の見え方が変わる「うつり変わっていくような空間性」をつくり出すことだ。絵の中のあるカタチからあるカタチへと視線を移動させるごとに画面の中の「中心」と「周辺」が入れ替わり、奥行き感や距離感の見え方が変化していくこの空間性は、透視図法的な空間とも平面的なものとも違う。
この画面の中であるカタチを見ようとする時には、見ることができない部分がある。そうした何かを見ようとする目の集中が、それによっては捉えられないものを意識させ、見えている以上の広がりをもたらす。そのことによってこの絵の空間は画面外へも届こうとする。
その空間性は、私が興味深く思っている風景の「誰かが自らの外の世界と接する場」としてのあり方とリンクしている。
風景は綺麗、心地よいということもあるが、もちろんそれだけではない。何者かの気配があったり、突然見知らぬものに出会うこともある。場合によっては自分を抜きにしても世界はまわっているという感覚を覚えることすらあるかもしれない。ただそのような時でも、その風景の場は自分の外側でまわっている(かもしれない)世界と自分を確実につないでいる。
私はそんな風景の場を描き出してみたい。
(2020.7.1)
© 2019 Haruka Kano